最近、農林水産省から「備蓄米の放出」に関する発表がありました。内容を簡単に言えば、「物価高で米の価格が高騰してるし、備蓄米を放出して市場を落ち着かせましょう」という政府の対策です。実際、米の価格はじわじわ上がってきていて、一般家庭や飲食店にはジワジワと影響が出てきているのを感じている人も多いはず。
ところが、いざ放出してもその米が市場に全然届いていない、という衝撃の実態が明らかになりました。
放出されたのに「届かない」備蓄米
農水省の調査によると、今回放出された備蓄米はおよそ14万トン。ところが、3月末時点で実際にJAや大手集荷業者が引き取ったのはたったの3%、約4000トン。さらにそのうち、小売店や飲食店まで流通したのは、わずか461トン。全体の0.3%です。もはや「どこに消えたの?」状態。
このニュースを見て、誰もが「え? 放出したって言ったじゃん?」「スーパーに全然安い米ないよ?」と思ったことでしょう。
江藤農水大臣の説明がツッコミどころ満載
で、問題はここから。江藤拓農水大臣はこの件について、
「備蓄米倉庫が東北に多く存在していることも事情としてあり、3月4月は人事異動の時期だったり、トラックの手配が難しかったりする部分もあった」
……と説明。ん? 本気で言ってます?
まず、「倉庫が東北にあるから」って、備蓄米が倉庫にあるのは当然のことだし、国の危機に備えてるなら、いざって時の配送体制も含めて備えておくべきでは?
さらに「人事異動の時期」って……。そんな理由が国の農業政策の現場で通用するなら、日本の食料安全保障ってめちゃくちゃ危ういんじゃないですか? 官僚の異動と物流の混乱で、必要な食料が届かない国って、どう考えてもおかしい。
もちろん、現場のトラック業者や倉庫担当者が頑張っているのは理解しています。ただ、それでも「理由がそれだけ?」というモヤモヤは残ります。
本当に困っているのは誰か
この備蓄米の放出、そもそもの目的は「価格高騰を抑えるため」でしたよね。でも、その米が市場に届かないなら、価格の安定なんて夢のまた夢。実際、米の価格は上がったままだし、安くなるどころか、外食産業や給食現場では「米の確保が難しい」という声も出てきています。
そして、一番しわ寄せが来るのは、日々の暮らしに直結する一般の人たちです。例えば、子育て世代や一人暮らしの高齢者。外食産業や小さな飲食店の店主。農水省の「説明」では、こうした人たちの不安や怒りに全く応えられていません。
「備える」という言葉の意味
「備蓄米」という制度は、本来、「いざという時」に私たちの生活を守るためのものです。でも、その「いざ」という時に機能しないのであれば、それはただの「倉庫に眠るお米」にすぎません。
そして、制度を動かすのは人。官僚や大臣が「システムとしてどう回すか」を真剣に考えなければ、どんな立派な制度も絵に描いた餅で終わります。
「人事異動だから」「トラックが足りないから」で済ませるのではなく、次の放出では、スムーズな物流と市場への速やかな反映が見られるよう、ぜひ現実的な対策をお願いしたいところです。
せめて、次回の記者会見では「ちゃんと届きました」という明るいニュースが聞きたいですね。
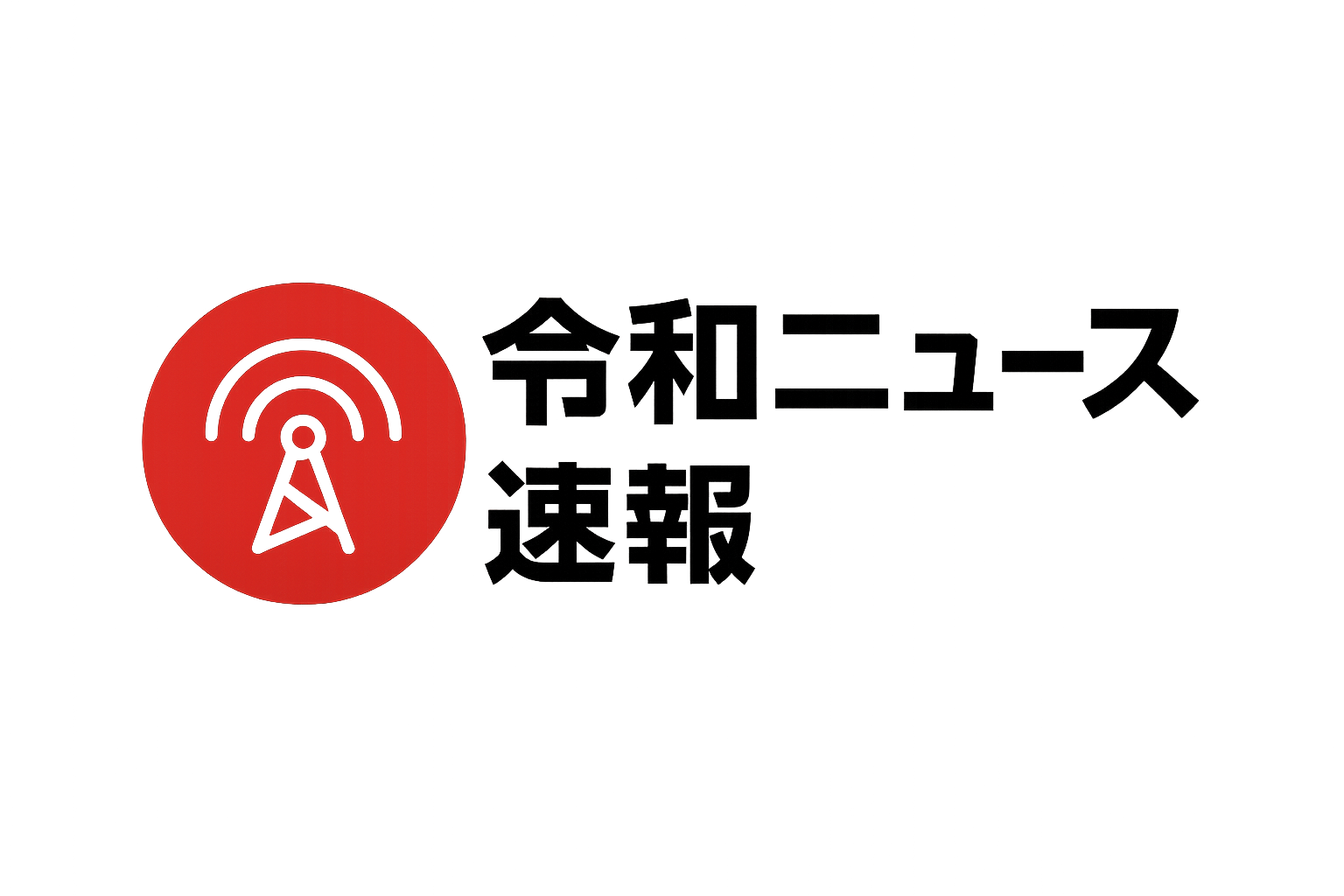
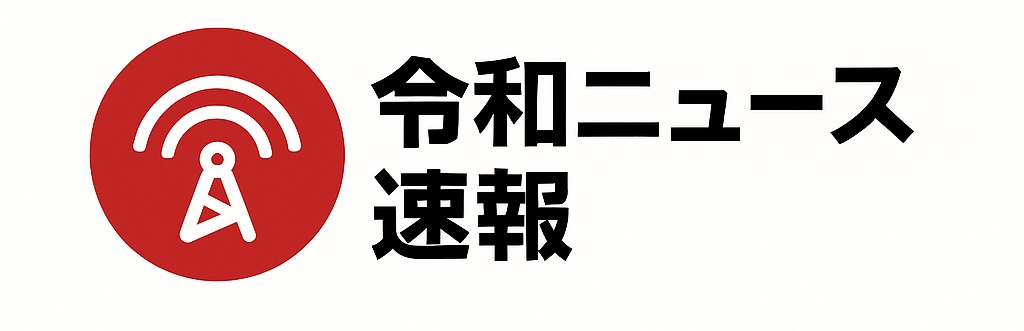


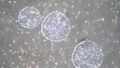
コメント