群馬県桐生市で、この10年間に生活保護の利用者が約半分、特に母子世帯では13分の1にまで激減していた。この数字だけを見ると「自立した人が増えたのかな」と思ってしまうかもしれない。しかし、実際にはとても深刻な問題が隠れていた。
2025年3月28日、桐生市の荒木恵司市長が記者会見で頭を下げた。「生活保護の申請権が侵害されていた」「市の対応で多くの方が苦しんだ」と謝罪したのだ。
なぜ、こんなことが起きたのか?
その背景には、役所の中で繰り返されていた「人権無視」の対応があった。
生活保護を「使わせない」市役所のやり方
本来、生活保護は国民の権利であり、困っている人が申請すれば、必ず書類を受け取り、審査を受けることができる制度だ。
ところが、桐生市では「申請書を渡さない」「受付しない」「親族に頼れと言って追い返す」といった対応が日常的に行われていたという。これらはすべて法律違反だ。
市の職員は、窓口に来た人に対して、「あいつらはくずだ」「働きたくないだけだ」といった侮辱的な言葉を使っていたことも、内部の証言で明らかになっている。まさに人権が踏みにじられていた。
第三者委員会が明かした「組織的な不正」
2024年から約1年間、桐生市ではこの問題を調査するために、法律や福祉の専門家による「第三者委員会」が作られた。そして2025年3月、その報告書が市に提出された。
報告書の中では、「生活保護法違反」「組織的な不正」「市の上層部による圧力」「職員の規範意識の崩壊」といった、非常に重い言葉が並んでいる。
単なる職員のミスや勘違いではない。市役所ぐるみで、制度を利用させないように動いていた、というのが報告書の結論だ。
「恥」や「甘え」ではない。生活保護は命を守る制度
生活保護に対する偏見は根強い。「楽してお金をもらっているだけ」「働かない人がもらうもの」といった考えが今でも広く残っている。
でも、実際には、病気やケガ、離婚、育児、DV、高齢など、さまざまな事情でどうしようもなく生活に困る人は多い。誰にでも、生活保護が必要になる可能性はある。明日は我が身なのだ。
そういうときに、国が最低限の生活を保証してくれる制度があることは、安心につながるはず。それなのに「申請させない」「恥をかかせる」「追い返す」ようなやり方は、命を切り捨てる行為にほかならない。
本当に減ったのは「利用者」ではなく「救われたはずの人たち」
桐生市で生活保護を受けていた母子家庭は、この10年で13分の1にまで減った。しかし、それは「困っている人がいなくなった」からではない。
申請しようとしても断られた人たちが、どこにも頼れず、我慢するしかなかった。ある人は借金を抱え、ある人は精神的に追い詰められたまま、声も上げられずに暮らしていた。
市の数字が良く見える裏側で、本当は「救われたはずの人たち」が静かに見捨てられていたのだ。
この問題は桐生市だけじゃない
今回の桐生市の問題は、氷山の一角かもしれない。他の自治体でも、申請しづらい雰囲気や、厳しすぎる対応があるという声は少なくない。
生活保護は「最後の砦」と言われているが、その砦にすらたどり着けない人がいる。しかも、それが市の職員によって意図的に妨げられていたのなら、これは国家としての責任にも関わる問題だ。
私たちにできること
このニュースを読んで、「ひどい」「信じられない」と思った人も多いと思う。でも、ここからどう行動するかが大事だ。
・生活保護は「権利」だということを知ること
・もし周りに困っている人がいたら、制度を使っていいと伝えること
・おかしな対応があれば、役所やメディアに声をあげること
無関心が一番怖い。制度は、ちゃんと声をあげる人がいることで守られる。
おわりに
桐生市で起きた生活保護の問題は、「数字の裏側」で何が起きていたかを私たちに突きつけている。申請を拒まれた人たちは、声を上げる余裕すらなかったかもしれない。そんな中でようやく事実が明らかになったことは、ほんの小さな一歩だ。
今後、桐生市がどう変わっていくのか。そして、私たちの社会がどこまで人を見捨てないでいられるのか。これは、他人事ではない私たち自身の問いでもある。
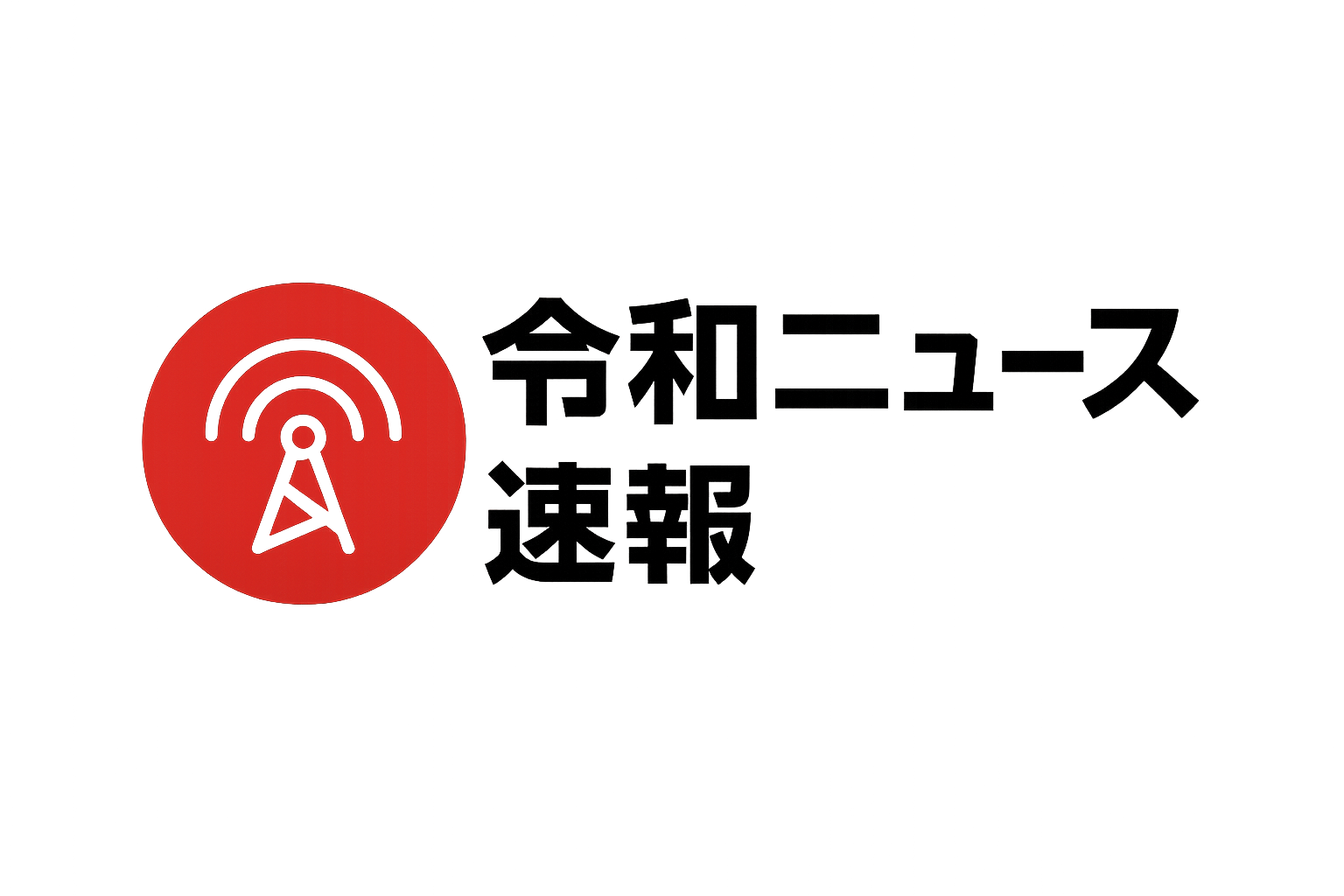
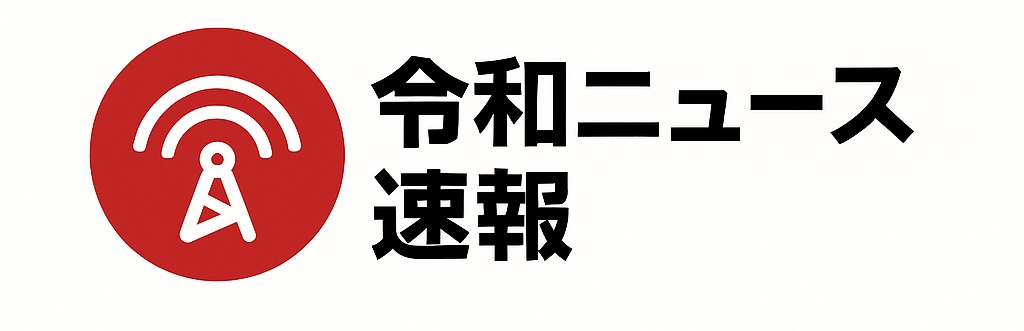



コメント