障害年金不支給の急増:何が起きているのか?
共同通信の調査によれば、2024年における精神・発達障害の障害年金申請に対する不支給率は、前年の2.2%から4.4%へと倍増しました。全体の障害種別でも不支給率は1.6倍に増加しています。このデータは、全国5県の社会保険労務士が取り扱った計2,000件超の申請を基にしています
日本年金機構は「審査方法などは変更しておらず、基準に基づき適正に判定している」と述べていますが、現場の社会保険労務士からは「明らかに判定が厳しくなった」との声が上がっています 。
背景にある可能性:審査の厳格化と地域差
障害年金の審査においては、特に精神・発達障害の判定が難しく、判定医の裁量によるばらつきが指摘されてきました。2016年には判定ガイドラインが導入されましたが、それでもなお地域による不支給率の差が存在しています。例えば、2012年度のデータでは、大分県の不支給率が24.4%であるのに対し、栃木県では4.0%と、約6倍の地域差が報告されています 。
このような地域差や審査の厳格化が、2024年度の不支給率増加の一因となっている可能性があります。
申請者が取るべき対策:正確な情報と専門家の活用
障害年金の申請においては、以下のポイントが重要とされています
- 信頼できる医療機関を選び、適切な診断書を取得する。
- 自身の症状や生活状況を正確に医師に伝える。
- 障害年金に関する最新の情報を収集し、制度の変更に対応する。
- 必要に応じて、社会保険労務士などの専門家に相談し、申請書類の作成を支援してもらう。
これらの対策を講じることで、審査の厳格化に対応し、受給の可能性を高めることができます。
結論:制度の透明性と申請者の対応が鍵
障害年金の不支給率の増加は、制度の運用や審査体制の課題を浮き彫りにしています。申請者自身が正確な情報を持ち、適切な対応を取ることが求められます。また、制度の透明性と公平性を確保するためには、国や関係機関による継続的な見直しと改善が不可欠です。
障害年金は、生活の安定を支える重要な制度です。今後もその適切な運用と、申請者への支援体制の強化が求められます。
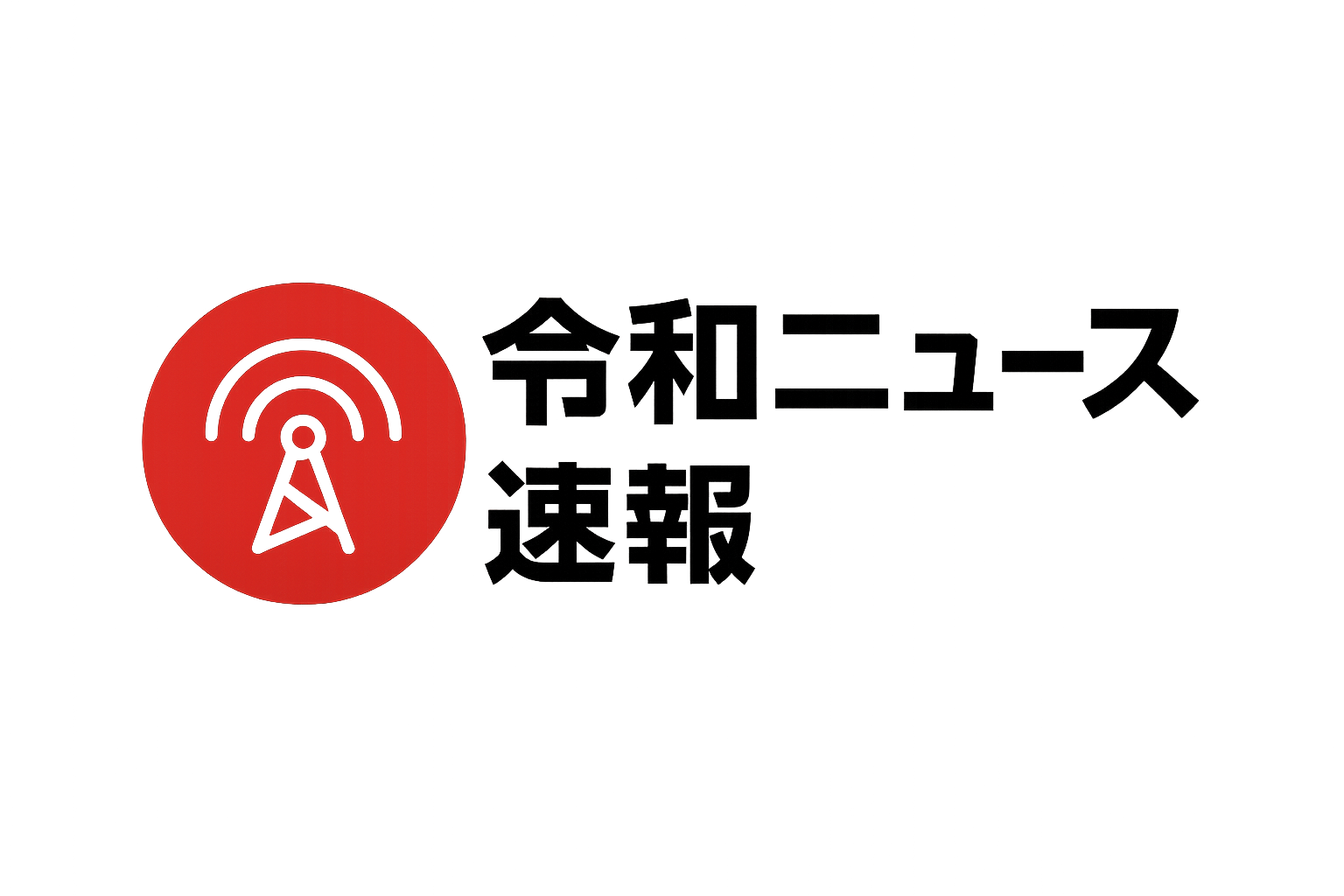
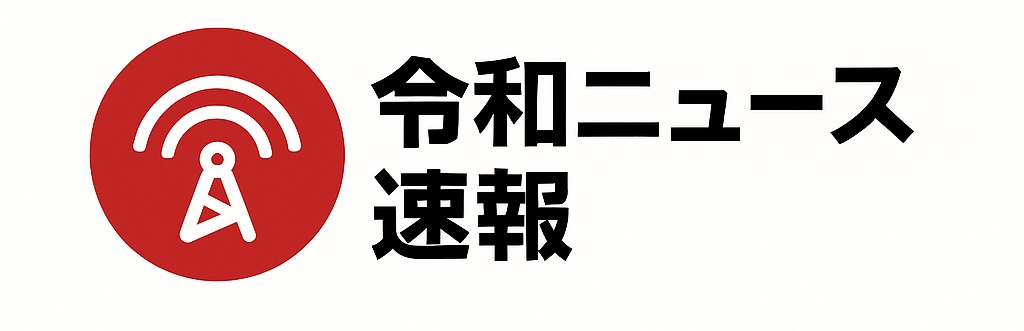
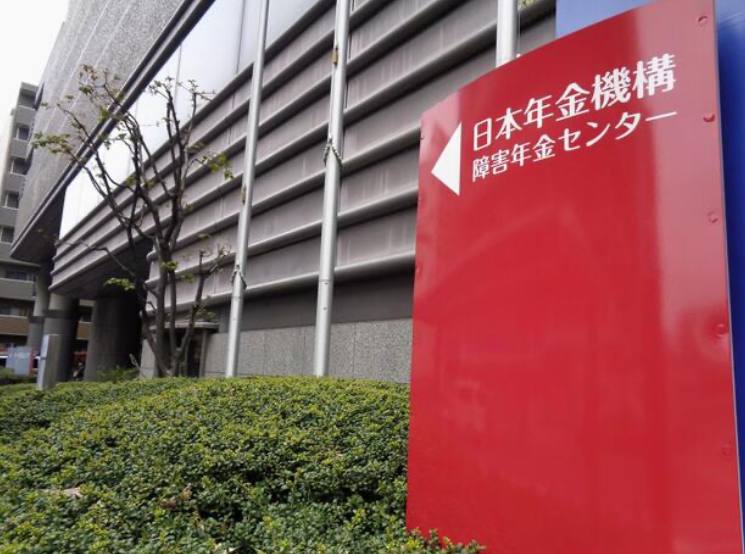


コメント